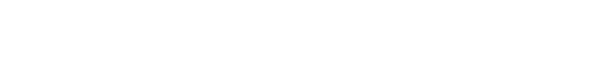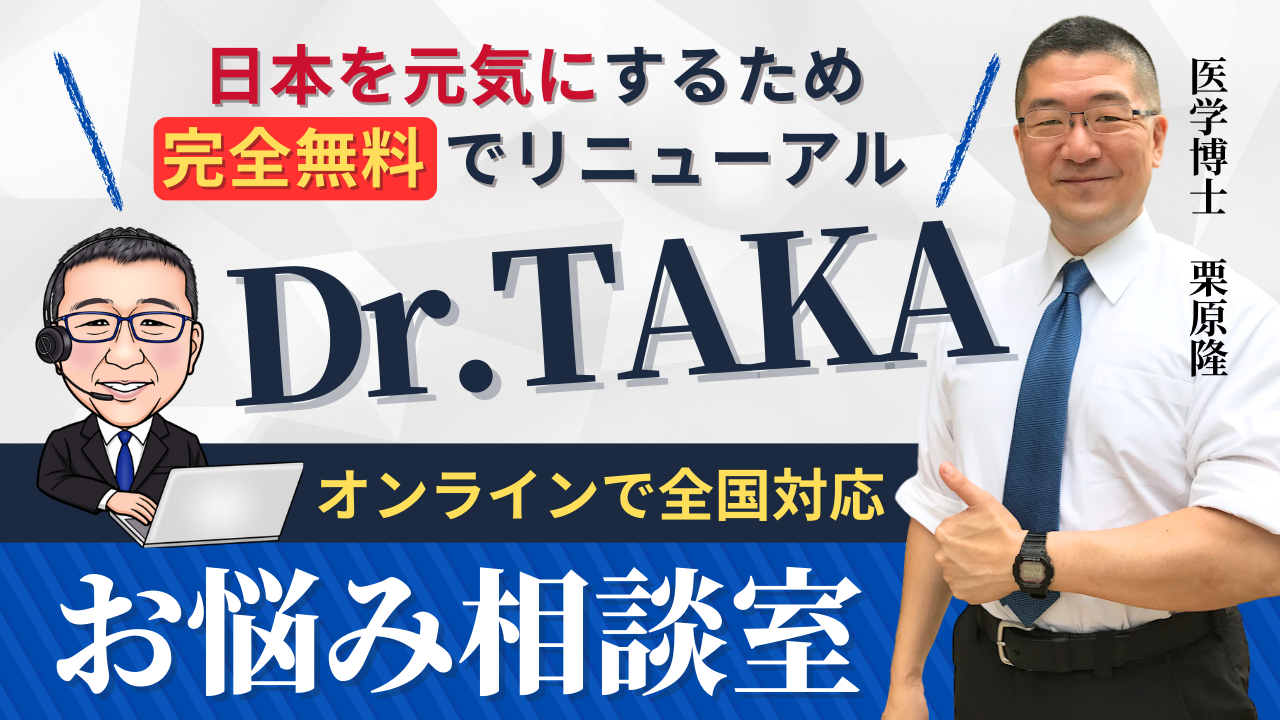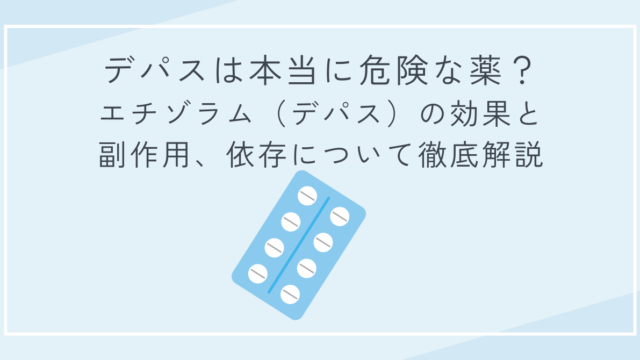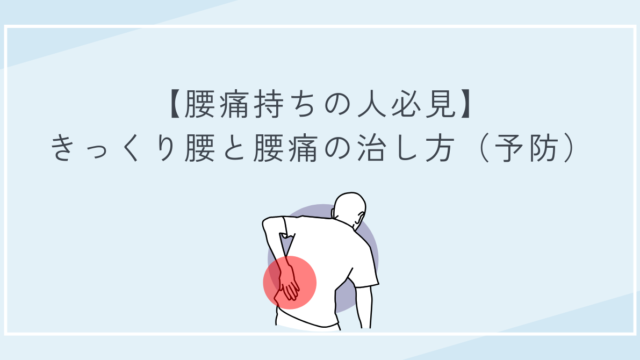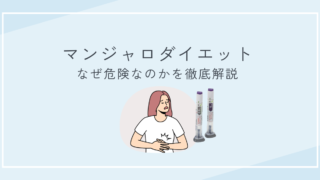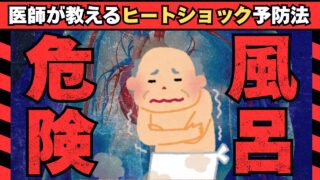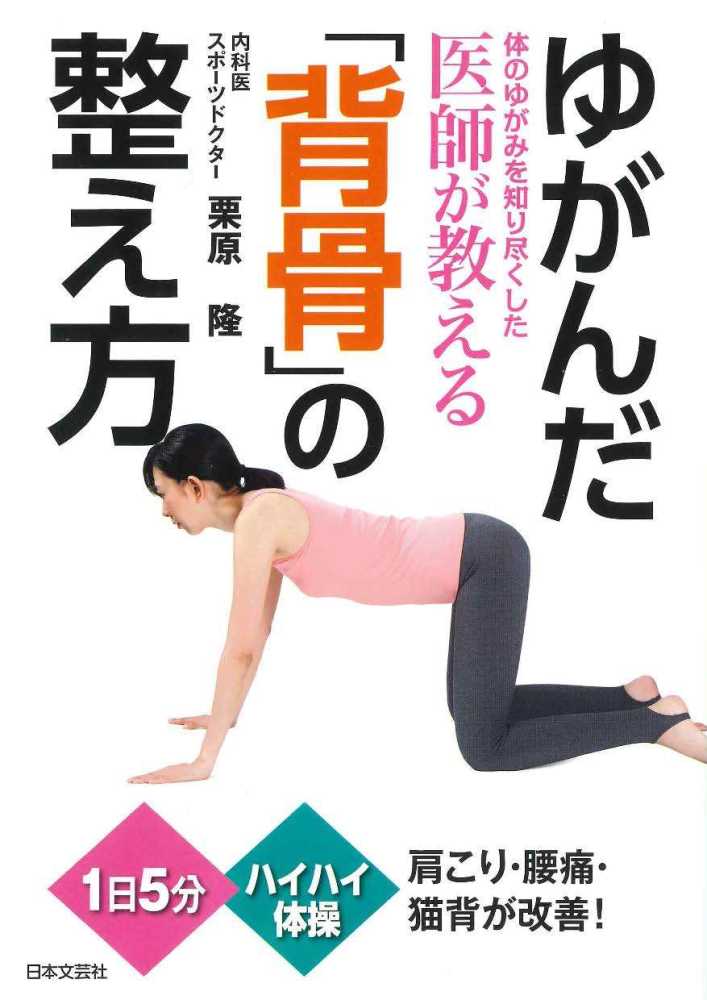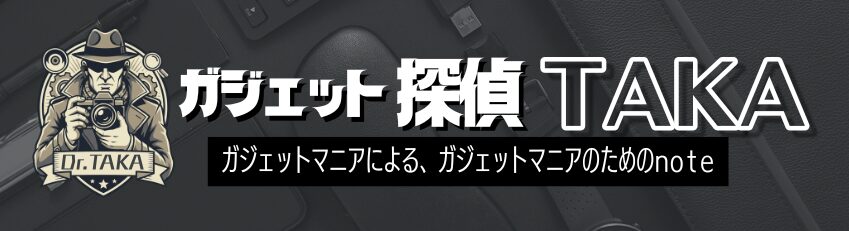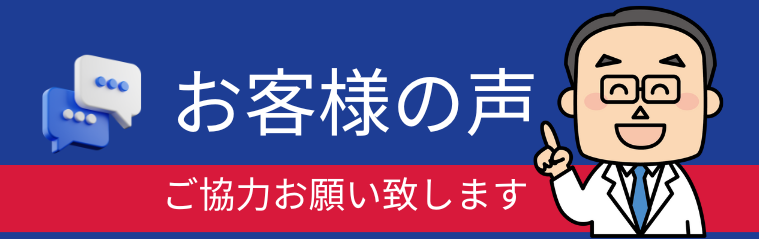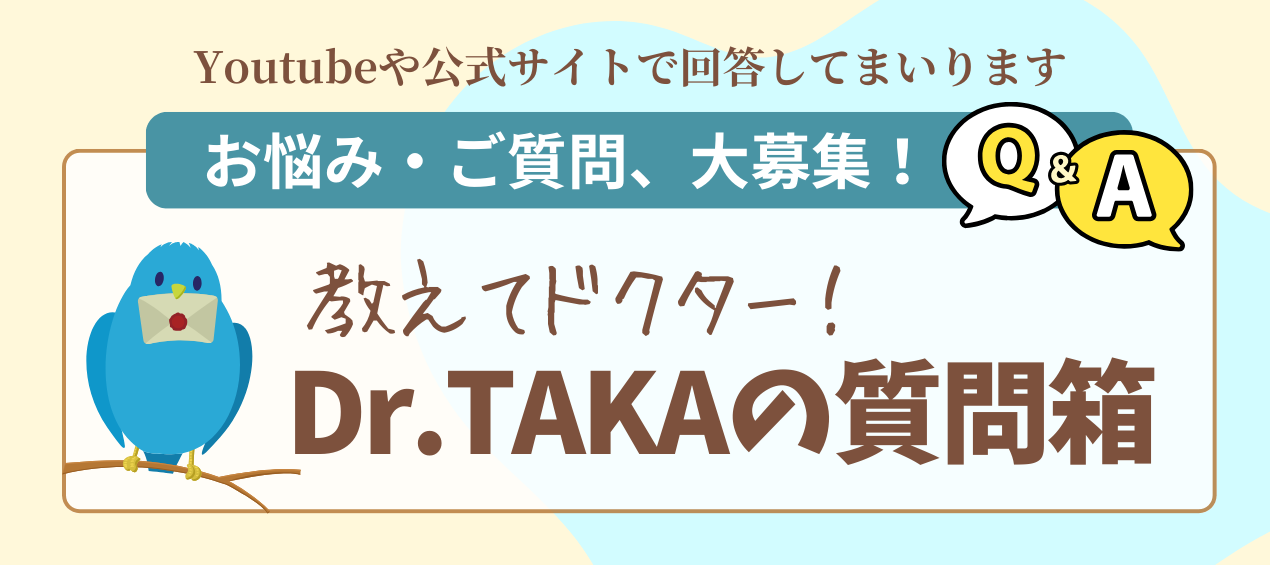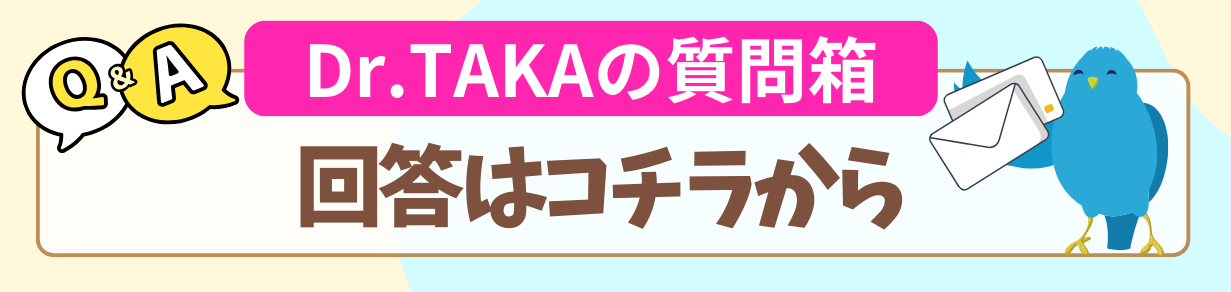こんにちは!Dr.TAKAこと内科医でスポーツドクターの栗原隆です。
高脂血症(脂質異常症)は、心筋梗塞や脳梗塞といった重篤な病気を引き起こす動脈硬化の大きな原因の一つです。健康診断で「コレステロール値が高い」と指摘された方も多いのではないでしょうか。
この記事では、脂質異常症の基礎知識から、原因、ご自身でできる改善方法、そしてどのような薬が使われるのかまでを、初心者の方にも分かりやすく解説します。
1. 脂質異常症(高脂血症)とは?
「脂質異常症」と「高脂血症」の違い
脂質異常症は、かつて高脂血症と呼ばれていた病気です。
現在、「脂質異常症」という名称が使われるようになったのは、単に血液中の脂質が高い状態だけでなく、善玉コレステロール(HDLコレステロール)が低い状態も含めて治療の対象とするためです。
脂質異常症とは、血液中の脂質(主にコレステロールと中性脂肪)が基準値から外れた状態のことを指します。
脂質異常症の3つのタイプ
脂質異常症は、どの脂質が異常値を示すかによって、主に次の3つのタイプに分けられます。
| タイプ | 異常な状態 | 診断基準値(空腹時採血) |
|---|---|---|
| 高LDLコレステロール血症 | 悪玉コレステロールが多い状態 | LDLコレステロール ≧ 140mg/dL |
| 低HDLコレステロール血症 | 善玉コレステロールが少ない状態 | HDLコレステロール < 40mg/dL |
| 高トリグリセリド血症 | 中性脂肪が多い状態 | トリグリセリド ≧ 150mg/dL |
これらの異常が単独で起こる場合も、複数が組み合わさって発症するケースもあります。
脂質異常症を放置する危険性
脂質異常症そのもので症状が出ることはまれですが、放置していると、動脈硬化を引き起こします。動脈硬化が進行すると、心筋梗塞や脳梗塞などの深刻な病気のリスクを高めてしまいます。
脂質異常症の主な原因と診断基準 🤔
主な原因
脂質異常症は、複数の原因が組み合わさって発症することが多いとされています。
- 生活習慣: 食生活の乱れ(脂肪や糖質の過剰摂取)、運動不足、喫煙、飲酒などが挙げられます。特に日本人では、食生活の欧米化や運動不足が大きな影響を与えていると言われています。
- 加齢: 年齢とともに脂質代謝が変化します。
- 遺伝的要因(原発性脂質異常症): 生活習慣に問題がなくても、家族性高コレステロール血症などの遺伝性疾患によって発症することがあります。
- 他の疾患(二次性脂質異常症): 糖尿病や甲状腺機能低下症などの病気が原因となることがあります。
- 薬剤: ステロイド薬などの薬剤の副作用も原因の一つです。
診断と受診の目安
脂質異常症の診断は、血液検査で行います。
診断基準(前述)の数値に当てはまる場合や、脂質異常症の家族歴がある方、高血圧や糖尿病などの動脈硬化に関連する持病を持つ方は、早めに医師の診察を受けることをおすすめします。
脂質異常症の予防と改善方法(生活習慣の改善)🎯
脂質異常症の治療において、薬物療法を開始する前に、食事や運動などの生活習慣の改善が最も重要とされています。
生活習慣の改善が治療の最初のステップです。
- 食事の改善 🥗
- 魚類や大豆製品、野菜、果物などを意識して食事メニューに取り入れましょう。
- コレステロールを多量に含む食品(卵、レバー、魚卵など)は摂取量に注意が必要です。
- 過度の食塩摂取にも注意してください。
- 適度な運動 🏃
- 速歩やジョギングなどの有酸素運動を毎日30分以上行うことが推奨されます。
- 肥満を解消することは、中性脂肪値の低下やHDLコレステロールの上昇につながります。
- 禁煙 🚭
- 喫煙は動脈硬化のリスクを高めるため、喫煙・受動喫煙ともに控えましょう。
- 過剰な飲酒を控える 🍺
- アルコール量は、1日あたり20〜25g以下(日本酒1合以下、ビール500mL以下)にしましょう。
脂質異常症の治療に使われるお薬(薬物療法)💊
生活習慣の改善だけでは十分な効果が得られない場合や、既に心筋梗塞などの病気を経験した場合、あるいは遺伝的に脂質異常症になりやすい体質の場合(家族性高コレステロール血症など)には、薬物療法が必要になります。
治療薬は、主に「コレステロール値を下げる薬」と「中性脂肪値を下げる薬」に分けられます。
A. コレステロール値を下げる薬(主にLDLを減らす薬)
治療の第一目標とされることが多いのは、LDLコレステロールの値を低下させることです。
- スタチン系薬
- 脂質異常症治療において、**最初に選ばれる薬(第一選択薬)**です。
- 体内の肝臓でコレステロールが合成されるのを抑え、悪玉コレステロール(LDLコレステロール)を下げる働きがあります。
- 強力なタイプ(ストロングスタチン:ロスバスタチン、アトルバスタチンなど)と標準タイプがあります。
- 主な副作用として、筋肉痛や肝機能障害などがあり、特に高齢者は注意が必要です。
- 小腸コレステロール吸収抑制薬
- 代表的な薬剤は**エゼチミブ(商品名:ゼチーア)**です。
- 食事から小腸でコレステロールが吸収されるのを選択的に阻害し、LDLコレステロールを低下させます。スタチンと併用されることも多く、より効果的なコントロールが期待できます。
- PCSK9阻害薬
- エボロクマブ(商品名:レパーサ)やアリロクマブ(商品名:プラルエント)などの注射タイプの薬です。
- スタチンで効果が十分でない場合や、家族性高コレステロール血症の治療に使われ、強力にコレステロールを低下させます。
B. 中性脂肪値を下げる薬
- フィブラート系薬
- 主に高トリグリセリド血症(高中性脂肪血症)の治療に用いられます。中性脂肪を低下させるとともに、HDLコレステロール(善玉)を上昇させる働きもあります。
- 代表的な薬剤にはペマフィブラートなどがあります。スタチンとの併用で筋肉の障害のリスクが高まるため注意が必要です。
- EPA/DHA製剤
- 魚の油に含まれる成分(エイコサペント酸エチル、オメガ-3脂肪酸エチルなど)から作られた薬です。
- 中性脂肪の合成を抑制し、いわゆる血液をサラサラにする作用があります。食事で魚を多く摂取することでも中性脂肪を低下させる効果が期待できますが、高トリグリセリド血症では薬として服用することがあります。
薬物療法をいつから始めるか?
薬物療法の開始時期は、日本動脈硬化学会のガイドラインに基づき、個人のリスク状態に応じて判断されます。
- 二次予防(すぐに開始)
- 既に心筋梗塞や狭心症などの冠動脈疾患の既往がある場合は、生活習慣の改善と同時に薬物療法を開始します。LDLコレステロール目標値は100mg/dL未満(70mg/dL未満が望ましい)と厳しく設定されます。
- 一次予防(生活習慣の改善から)
- 上記以外の場合は、まず生活習慣の改善を行い、効果が不十分な場合に薬物療法を検討します。
- ただし、LDLコレステロールが180mg/dL以上の場合は薬物療法も検討が必要です。
- 特に家族性高コレステロール血症では、動脈硬化予防のため、早期の薬物療法が推奨されています。
まとめ
脂質異常症は、自覚症状がないまま進行し、動脈硬化を通じて命に関わる疾患を引き起こす可能性がある病気です。
まずは、禁煙、適度な運動、食事の改善といった生活習慣の見直しから始めましょう。生活習慣の改善でも十分な効果が得られない場合は、医師と相談して薬物療法を開始します。
定期的な血液検査で脂質の値をチェックし、医師と相談しながら治療を続けることが大切です。ご自身の健康管理について理解を深め、主治医と信頼関係を築きながら治療を進めていきましょう。
12月13日リリース