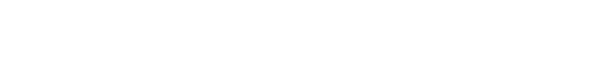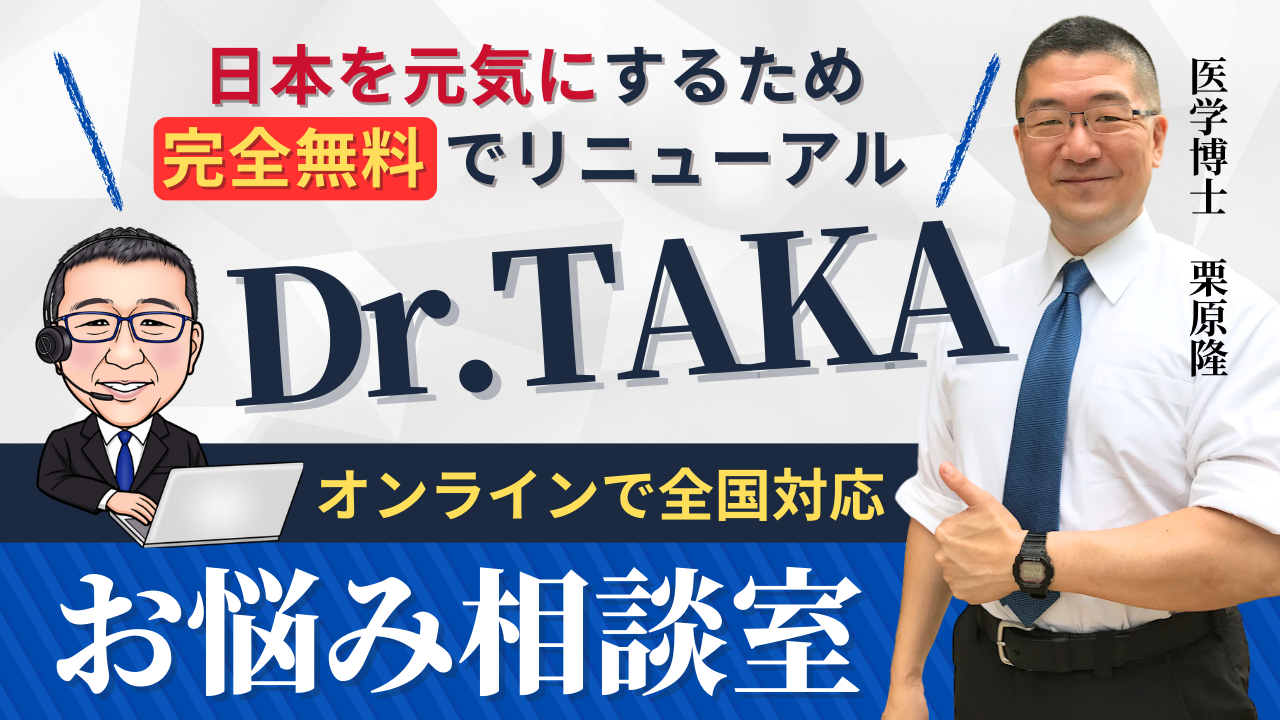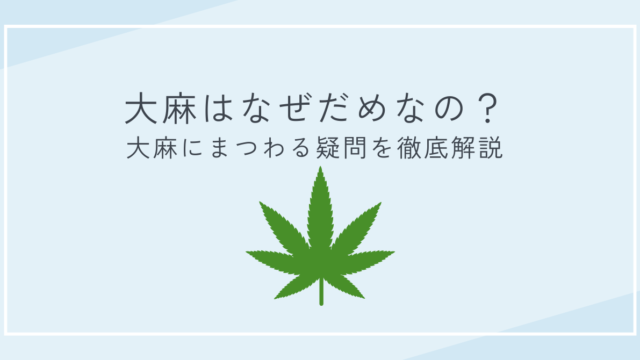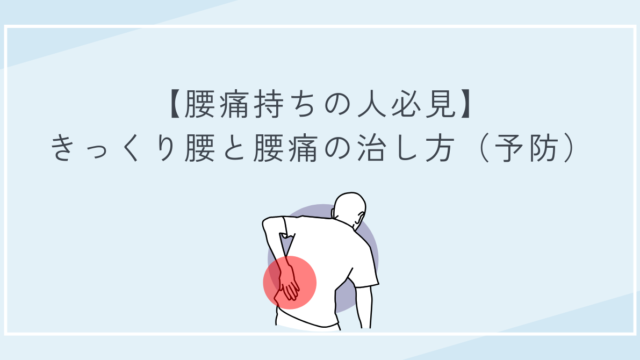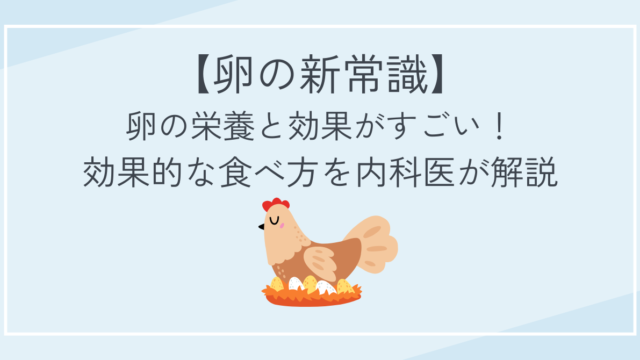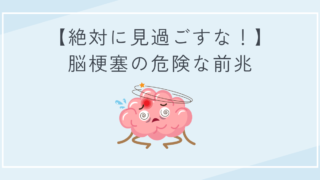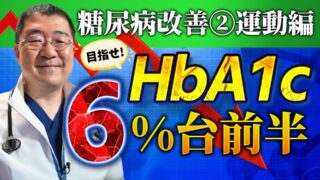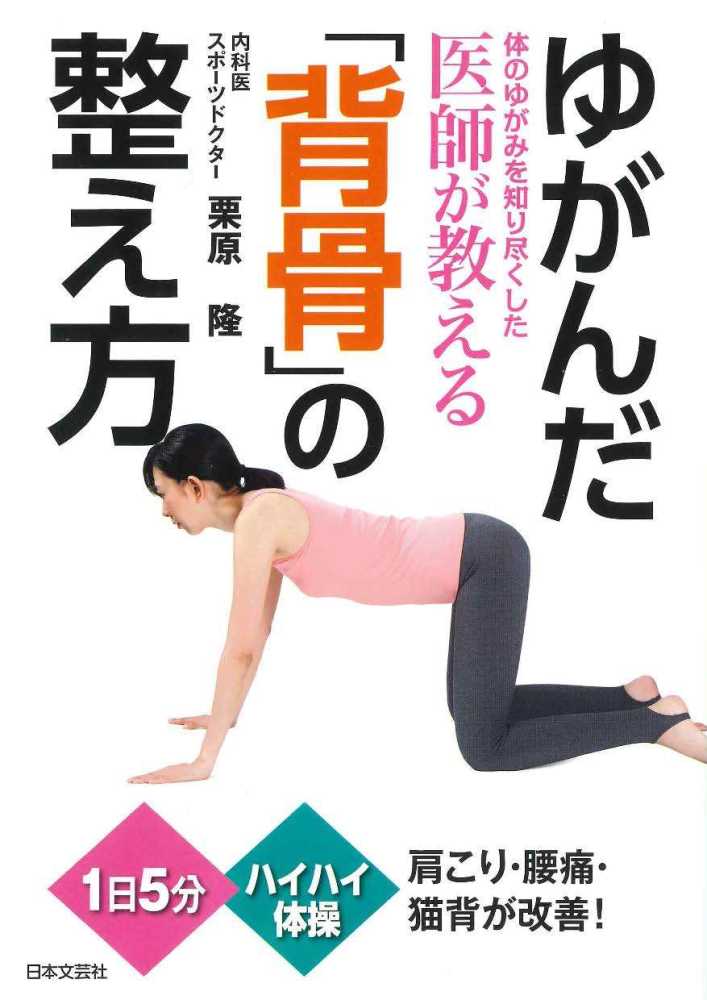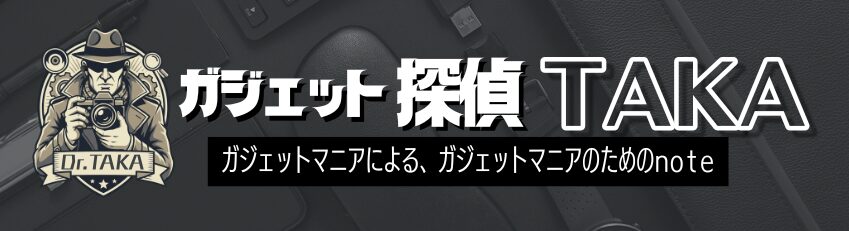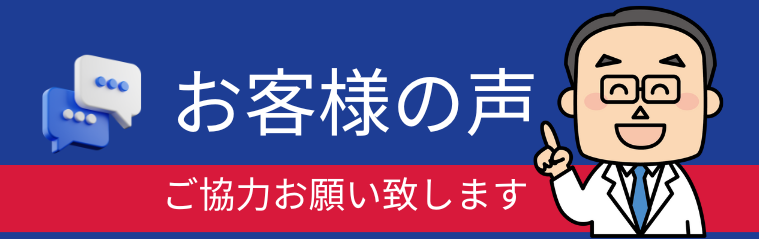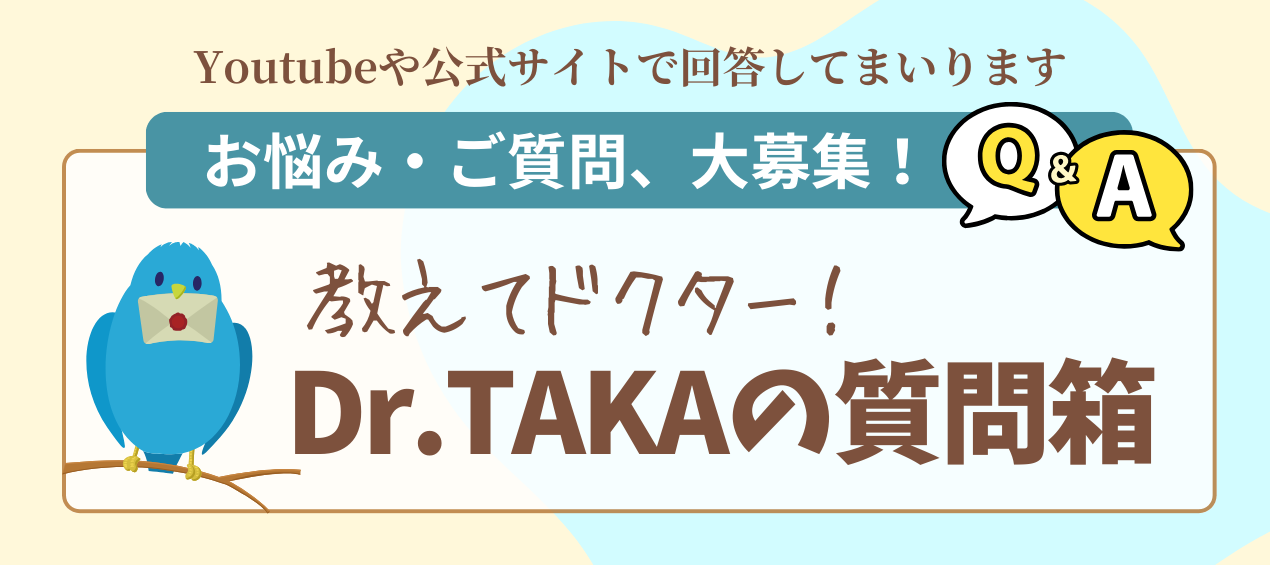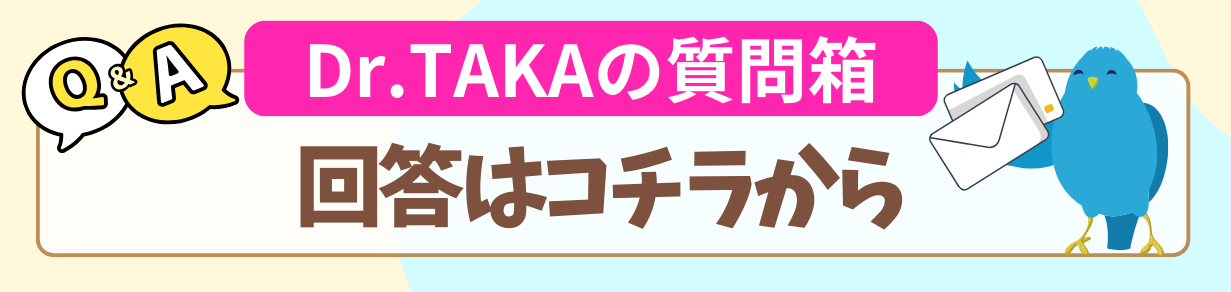みなさん、こんにちは!Dr.TAKAこと内科医でスポーツドクターの栗原隆です。
今回は、よくご相談いただく「ヘモグロビンA1c(HbA1c)を下げたい」というお悩みについて、専門家の立場から具体的な方法をお伝えしてまいります。
HbA1cとは?6%台を目指す理由
HbA1c(ヘモグロビンA1c)とは、過去1〜2ヶ月の血糖値の平均を示す指標です。
血液中のヘモグロビンがブドウ糖と結びついた状態を測定することで、血糖の変動を反映します。日々の食事や運動による一時的な影響を受けにくいため、長期的な血糖コントロールの目安として広く使われています。
この数値が高い状態が続くと、糖尿病性の神経障害、網膜症、腎機能障害による透析など、糖尿病による合併症のリスクが急上昇してしまいます。
目標は「安全なゾーン」6%台前半
- 一般的に健康な人のHbA1cは4.6%から5.6%ぐらいです。
- 糖尿病の診断基準は、大体6.5%以上とされています。
- 6%台前半は、糖尿病の診断基準を下回り、合併症リスクも低く抑えられる「安全なゾーン」と考えられています。
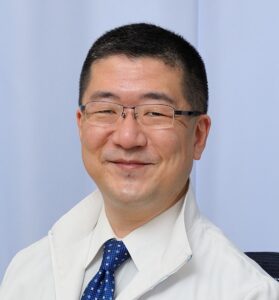
- 合併症の発症のリスクが大きく下がる。
- 薬を減らしたり、やめたりしやすい。
- 無理な食事制限や低血糖のリスクを避けつつ、現実的に達成しやすい。
HbA1cを6%台に保つためには、まず「なぜ自分はうまくいかないのか」という原因を理解することが大切です。
【失敗パターン1】極端な糖質制限に注意!
ここからは、糖尿病の改善がうまくいかない人に共通するポイントをお伝えします。
自力で血糖値の改善がうまくいかない人の共通点で最も多い理由は、糖質を極端に制限しているというパターンです。誤った糖質制限を行う人が増えています。
極端な制限が招く悪循環
- 糖質制限を頑張りすぎて白米やパンを完全にカットする人が外来でも時々います。
- 脳に必要な糖(グリコーゲン)が足りなくなり、頭がぼーっとしたり、イライラしたりします。
- イライラの反動で爆食してしまうと、リバウンドの典型的なパターンに陥りやすいです。
- また、糖質を完全に抜くと、その分おかずが増え、脂質の摂取量が増えることによってカロリーオーバーになりやすくもなります。
対策:糖質は最低限摂取し、自分なりのルールを決める
 ご飯のカロリーは160g (1膳)で250kcal
ご飯のカロリーは160g (1膳)で250kcal1食あたり、ご飯は最低でも100g程度は食べることを心がけてみてください。
また、糖質と脂質の組み合わせ(例えば、スナック菓子やラーメン)はカロリーオーバーになりやすいので、できる限り避けた方が無難です。
ただし、どうしても食べたい場合は、週に1回や2回など、自分なりのルールを最低限決めておくと良いでしょう。
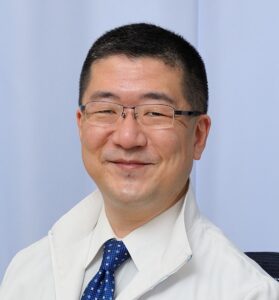
【失敗パターン2】適正カロリーの不把握が改善を妨げる
次に多いのは、自分にとっての適正カロリーを把握していないというパターンです。
野菜多めや糖質制限が良いという話ばかりに意識が向きがちですが、野菜多めや糖質だけを抜くなどでは、血糖値は安定しません。
糖尿病を改善させるには、昔から言われている基本中の基本、総摂取カロリーを把握して管理することがとても大切です。
あなたの目安カロリーを計算してみよう
総摂取カロリーを把握するために、標準体重と1日の目安カロリーを計算してみましょう(例:身長160cm、体重80kgの方の場合)。
1. 標準体重の計算
身長160cmをm換算して計算します。
1.60m × 1.60m × 22 = 56.3 kg (標準体重)
例えば体重80kgの方は、標準体重より約23.7kg多いため、糖尿病や高血圧などの生活習慣病になるリスクが高い状態です。
2. 1日の目安カロリーの計算
運動量に応じて、標準体重(56.3kg)に係数をかけて計算します。
| 運動量 | 係数 | 計算(56.3kgの場合) | 目安カロリー |
|---|---|---|---|
| 運動が少なめ(デスクワーク) | 25 | 56.3 × 25 | 約1,408 kcal |
| 普通(運動や立ち仕事を少しする) | 30 | 56.3 × 30 | 約1,689 kcal |
| 運動が多め(肉体労働、スポーツ習慣) | 35 | 56.3 × 35 | 約1,970 kcal |
食事の量や摂取カロリーを見直し、目安になるカロリーを超えない範囲内で食事をコントロールすることが、血糖値やHbA1cを改善させるための第一歩になります。
血糖値改善の第一歩:食事記録(レコーディングダイエット)のすすめ
総摂取カロリーを把握するための具体的な方法として、食事記録が有効です。
まずは3日間!アプリで食事を記録しよう
今はカロリーだけでなく、様々な栄養素の表示や計算管理ができる便利なアプリ(例えば、アスケンやカロミル)が多いので、まずは3日間だけでも良いので食事記録をつけてみましょう。もちろん、昔ながらのノートに記録する方法でも構いません。
これは「レコーディングダイエット」と呼ばれる方法です。
レコーディング🐷ダイエット
レコーディングダイエットは2006年4月頃から岡田斗司夫さんが実践開発したダイエット法の一つで、日々摂取する食べ物とそのエネルギー量を記録することで、自分が摂取しているエネルギー量、食事の内容、間食などを自覚し、食生活の改善につなげるというものです。
特に、間食を多く取ったり、糖分の多い飲み物をたくさん飲んだりしている方は、目安になるカロリーを大きく超えていることに気づくことができます。
まとめ
まずは3日間、自分が何をどれくらい食べているのかを記録し、意識するようにしてみましょう。だんだん慣れてくると、記録をつけなくても、食材ごとのカロリー、タンパク質量、糖質量、脂質量、栄養素などが記憶され、自分が食べているもののカロリーや栄養成分が自然に分かるようになってきます。
Dr.TAKA
12月13日リリース