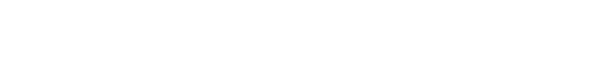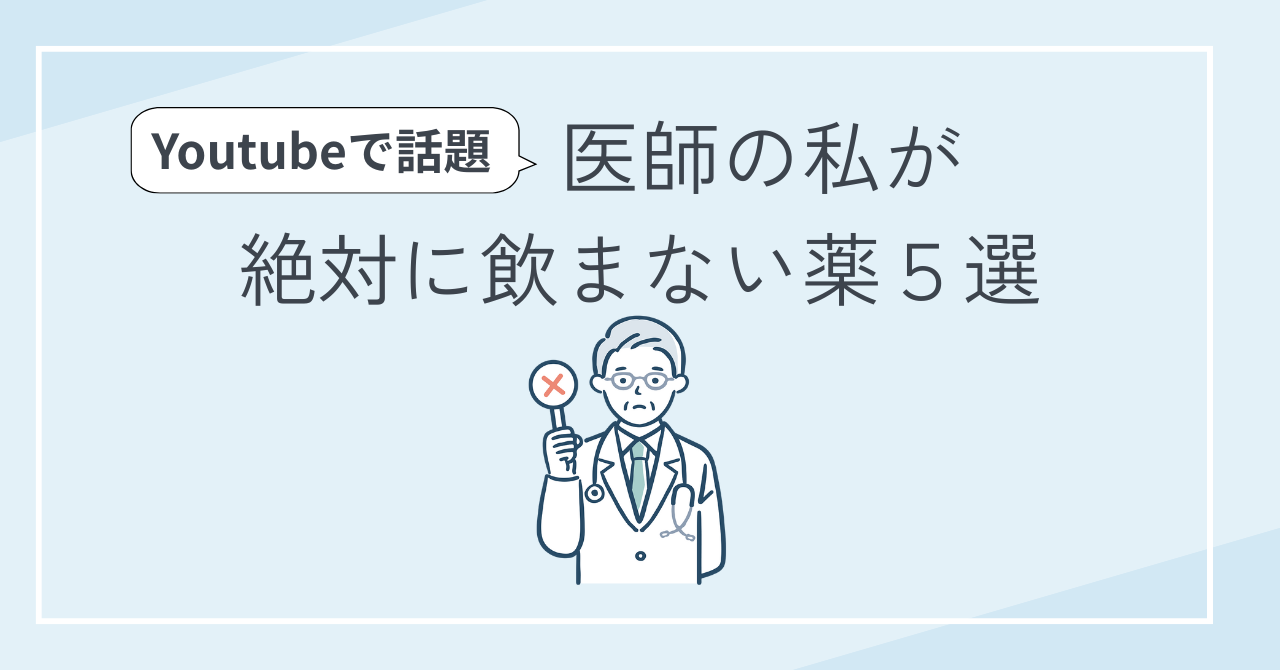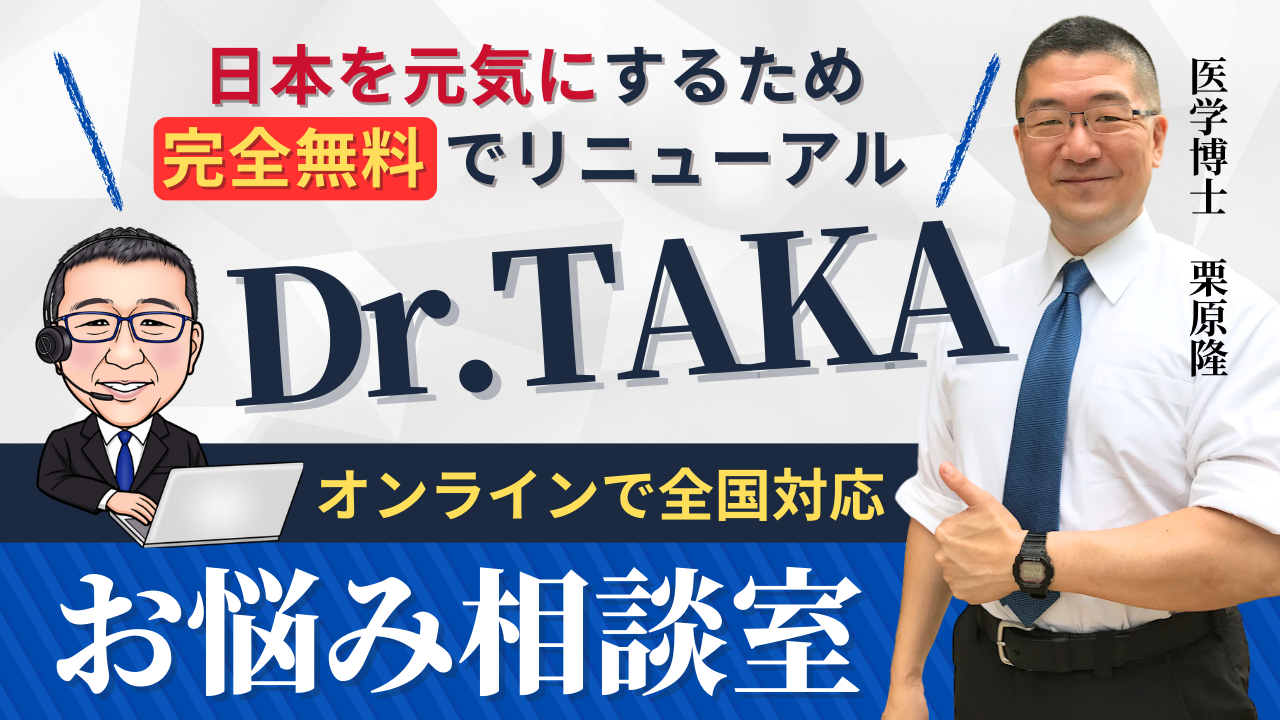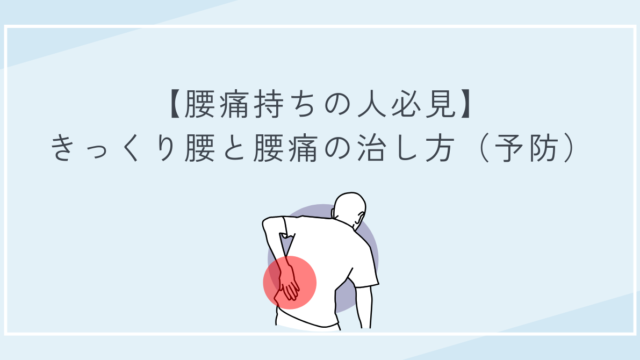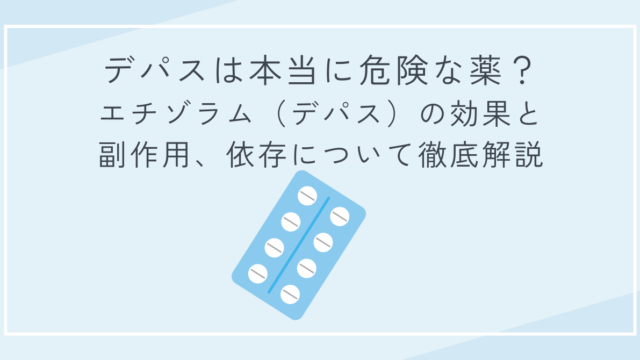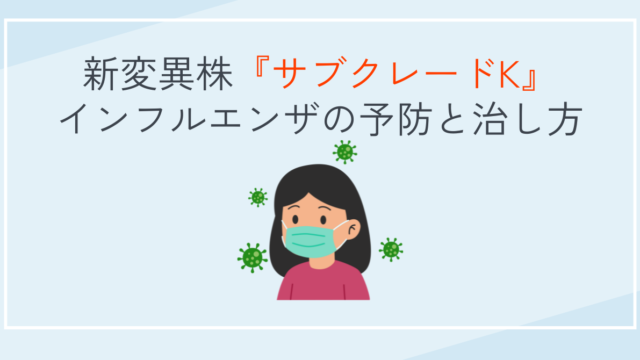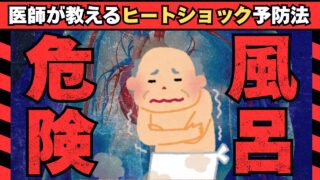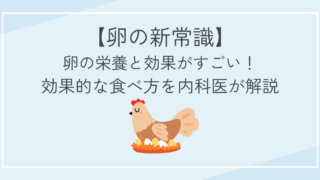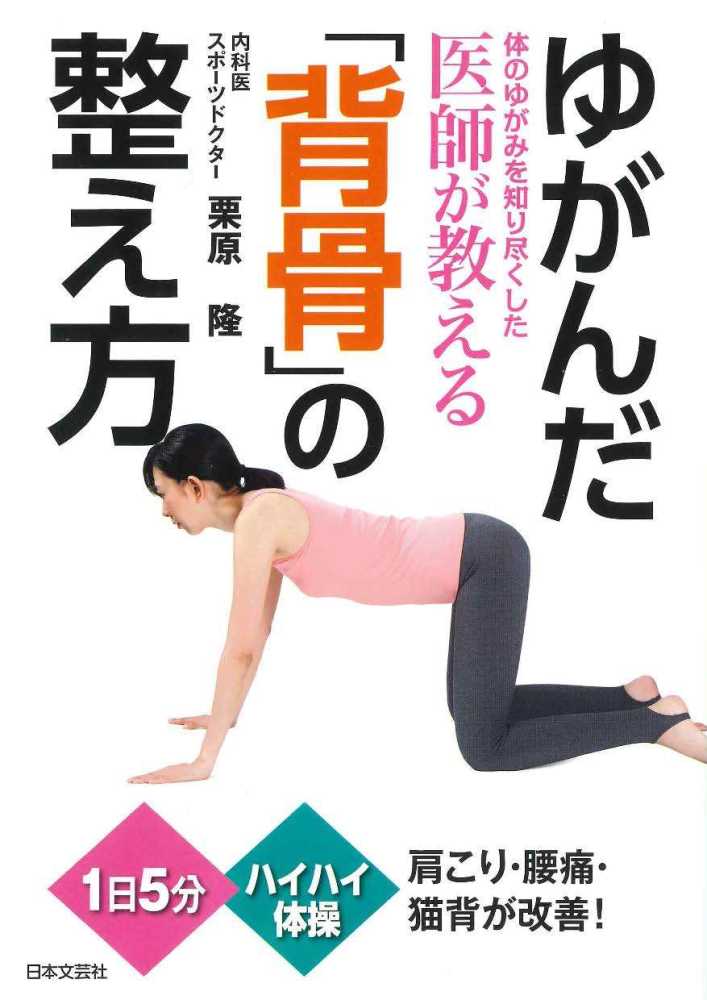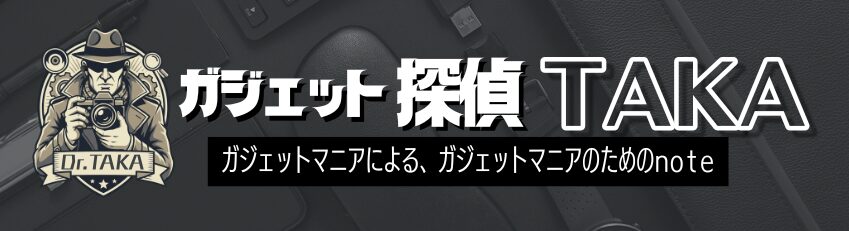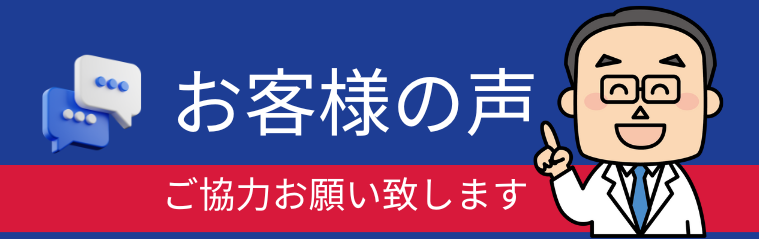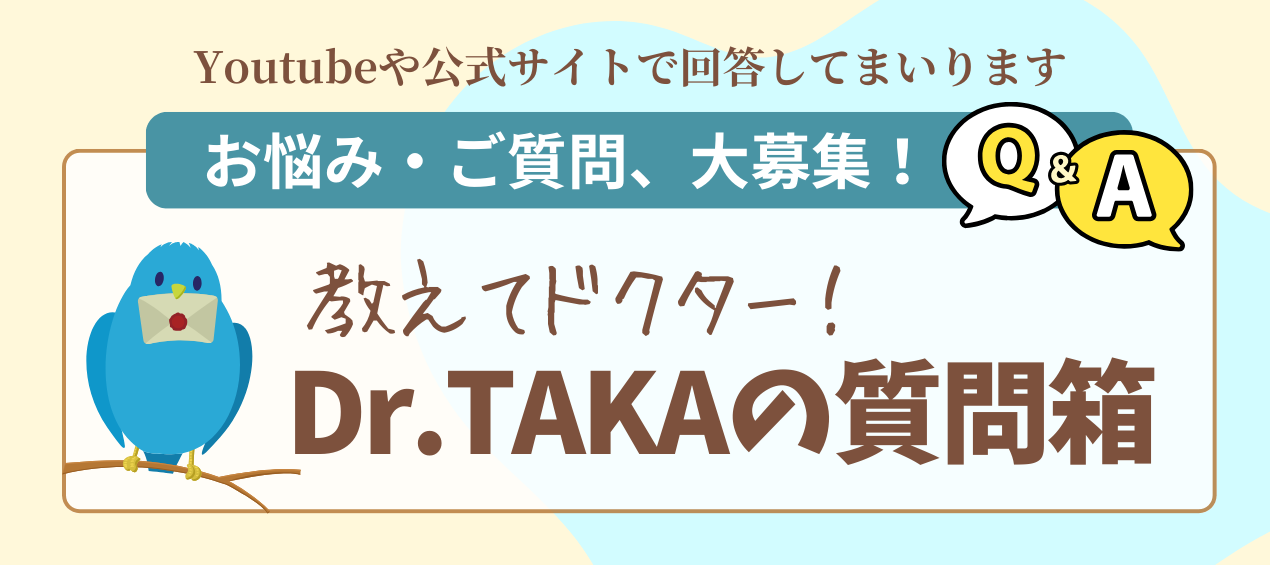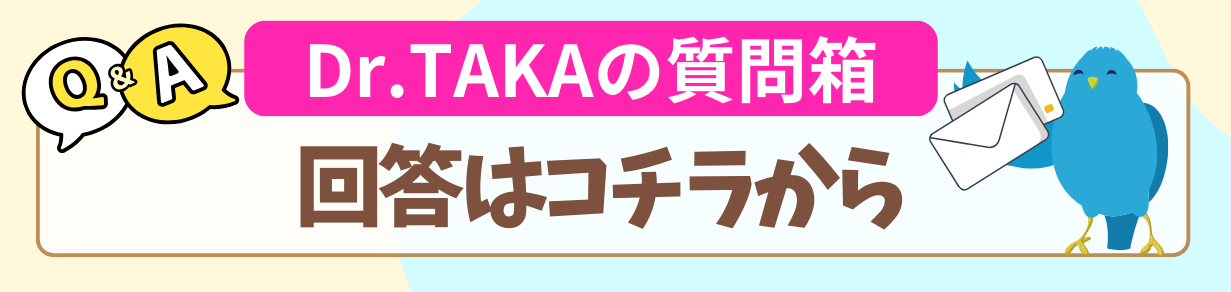こんにちは!Dr.TAKAこと内科医の栗原隆(生活習慣病の専門家)です。
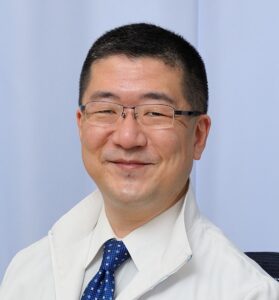
【ご質問より一部抜粋】「医者がの飲まない薬〇選」という動画をよく目にしますが、Dr.TAKA先生が飲みたくない薬などあればおしえてください。
私自身、医師として薬の効果はもちろん認識していますが、クスリを反対から読むと「リスク」(副作用)と読めますよね。薬を飲むことによる利益(ベネフィット)と副作用のバランスが非常に大切です。
医学的なデータや体のメカニズムを考慮すると、「割に合わない」と判断し避ける薬が実際にあります。というわけで、皆さんがよかれと思って飲んでいるけれども、数字で見るとリスクが高いかもしれない薬を5つ、エビデンスを交えて解説します。
【重要なお願い】 すでにこれらの薬を飲んでいらっしゃる方は、絶対に自己判断で急に服用をやめないでください。この情報を見た後で、主治医の先生に相談する材料として活用してください。
第5位 総合感冒薬(市販の風邪薬)
第5位は、ドラッグストアでよく売られている「総合感冒薬」です。
この薬が避けられる理由として、脳などに不要なダメージを与える成分が含まれており、そのことによるリスクがあるためです。
- 高齢者へのリスク: 一般的な総合感冒薬には「抗ヒスタミン薬」が含まれていますが、特に古いタイプの第1世代のものは、脳の神経伝達物質などに影響を与えやすいです。高齢者が飲むと、認知機能が低下してしまったり、強い眠気を起こして転倒・骨折するリスクがあります。
- 重篤な病気を引き起こす可能性: 古い成分であるサリサ系のお薬がインフルエンザ流行時に含まれている場合、ライ症候群やインフルエンザ脳症(脳が腫れてしまうような重篤な病気)を引き起こす関連性が指摘されています。

総合薬は、咳、鼻水、熱などの成分がごちゃ混ぜにされているため、自分に不要なリスクまで取り込んでしまう可能性があります。単一の症状(例:鼻水)がある場合は、その症状に特化した薬を選ぶか、基本的には栄養や睡眠といったもので治していくことが重要です。
第4位 安易な鎮痛薬|NSAIDs(ロキソニン、イブプロフェンなど)
ロキソニンやイブプロフェンといった「NSAIDs(非ステロイド性抗炎症薬)」と呼ばれるタイプの痛み止めを常用することは避けるべきです。
- 心臓への負担: ビッグデータの解析によると、このタイプの痛み止めを長期間使用していると、心不全のリスクが約20%高くなると言われています。
- 腎臓へのダメージとむくみ: Nセズは腎臓の血流を悪くする作用があり、体内にナトリウム(塩分)と水分を溜め込ませる作用があります。その結果、血液量が増えて心臓に負担がかかり、むくみや心不全につながる可能性があります。
- 薬剤誘発頭痛: 毎日常用するような使い方をすると、逆に頭痛を誘発する「薬剤誘発頭痛」の危険性もあります。
- 免疫反応の阻害: 風邪の時に使用するのも推奨できません。体に起きている炎症は、ウイルスなどと戦うための免疫反応であり、薬で無理やり抑えすぎると、免疫細胞の活性化が妨げられ、結果的に治りが悪くなる可能性もあります。
「毎日飲む」といった頻度での服用は避けるべきで、臨床の現場でも、毎日痛み止めが手放せず薬剤誘発頭痛になってしまうケースが多く見られます。
第3位 漫然と飲む胃酸を抑えるお薬|プロトンポンプ阻害薬(PPI)
第3位は、特に「PPI(プロトンポンプ阻害薬)」という強力な胃酸を抑える薬で、逆流性食道炎の治療として何年も出され続けているケースがあり、非常に要注意です。
胃酸には、食べ物に入っている菌を殺菌することと、ミネラルなどの吸収を促進するという、二つの大切な役割があります。そのため、薬で強力に胃酸の分泌をブロックし続けてしまうと、様々なリスクが生じます。
- 感染症のリスク増加: 殺菌作用が失われることで、肺炎や腸炎のリスクが上昇します。
- 骨折のリスク: カルシウム、マグネシウム、鉄分といったミネラル分が吸収できなくなり、結果として骨粗鬆症や骨折のリスクが上がることが分かっています。
- 胃がんのリスク: あるデータでは、胃がんのリスクを最大8倍も高める可能性も指摘されています。
必要な治療期間だけ飲むのは良いのですが、「なんとなく飲み続けている」状態は非常にハイリスクです。
ガスター(H2ブロッカー)よりも強力に胃酸を抑えるPPI(例えばタケプロンなど)は、特に注意が必要です。漫然と服用せず、時々は主治医の先生に処方の見直しを確認することが大切です。
第2位 ベンゾジアゼピン系の睡眠薬・抗不安薬
第2位は、ベンゾジアゼピン系の睡眠薬や抗不安薬です。これらは安易に飲むことが良くないとされています。
- 転倒・骨折のリスク: この系統の薬には「筋弛緩作用」(筋肉を緩める作用)があります。特に高齢者の場合、夜中にトイレに起きた際、筋肉に力が入らず転んでしまい、骨折して寝たきりになるという事故が非常に多いです。この転倒リスクは、服用していない時の数倍から数百倍とも言われています。
- 依存性と耐性: 飲み続けると、同じ量では効かなくなってくる「耐性」や、やめようとすると離脱症状で余計に眠れなくなる「依存」が問題となります。
- 認知機能への影響: 長期服用は、認知機能への悪影響や、認知症のように見えてしまう「せん妄」の原因になることも明らかになっています。
眠れないからと安易に薬に頼る前に、まずは生活リズムの改善などから取り組むことが大切です。
第1位 予防目的のスタチン(コレステロール低下薬)
第1位は「予防目的のスタチン」(コレステロール低下薬)です。
これは、過去に心筋梗塞を起こしたことのある人(再発予防で飲むべき人)ではなく、まだ病気になっていない人が健康診断でコレステロールが高いという理由で予防のために飲む場合についてのリスクです。
- わずかな予防効果: 大規模試験のデータを見ると、予防目的でスタチンを飲む場合、心臓発作を防げる効果は、相対リスクでは30%減ると言われていますが、絶対リスクではわずか1%程度にとどまります。
- 100人に1人の差: これは、飲まない人の心筋梗塞発症率が3%だったのが、飲んだ人で2%になった、つまり100人に1人が助かるかどうかの差だということです。このわずかなメリットのために、副作用を受け入れるかが難しい判断となります。
- 主な副作用:
- 横紋筋融解症(筋肉が溶けてしまう)。
- エネルギーを作るミトコンドリアの機能低下(CoQ10などが減る)。
- 糖尿病のリスクを上昇させる。
様々なデメリットがある中でスタチン系の薬を飲むのか、それとも薬に頼る前に食事と運動で改善するかどうかを判断することが非常に大切です。
結論:安易に薬に頼るべからず
お薬には必ず作用と副作用があります。本日ご紹介したお薬は、あくまでも漫然と長期服用した時のリスクについてのお話です。
最も危険なのは、何も考えないで飲み続けている場合です。
もし、これらの薬を服用していて不安に感じた場合は、勝手に中断するのではなく、次回の診察時に主治医に対し、「今の私の状態で、このお薬のメリットはリスクを上回っていますか?」といった質問をすることで、処方の整理につながるでしょう。
12月13日リリース